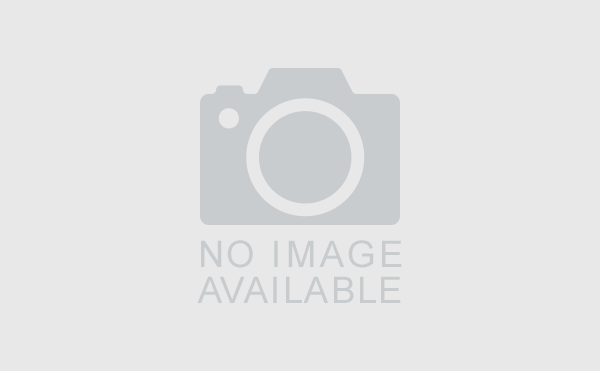高齢者に多い疾患の理解と必要性
こんにちは福祉タクシーひかりです。
友人との食事会でブログの更新が9月以降すすんでいないことを教えていただき、「そういえば‼・・・」と反省しております。
本日はタクシーネタからは少し離れ、高齢者に多い疾患について、ブログをまとめてみよう思います。
今回は死因別疾患の七大疾病にも入る高血圧性疾患についてです。
日本では約4300万人の方が高血圧と推定されており、脳卒中、心臓病、腎臓病の強力な原因疾患です。
一般的に無症状のことが多いですが、高血圧自体の症状としては、動機、息切れなどがあり、脳の細動脈硬化により脳の循環障害をきたすと、頭痛、めまい、耳鳴りなどを引き起こすことがあります。
高血圧治療は、生活習慣の見直しと降圧剤治療により行われます。
血圧値は大きく2つに分類した場合、正常域血圧と高血圧に分けられます。
高血圧は血圧の高さによりⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分けられます。血圧が高くなるにつれ、Ⅰ~Ⅲの数値が大きくなります。
高血圧の予防、悪化防止に必要なことは皆さんご存じの通り、生活習慣の改善です。
減塩、野菜・果物の積極的摂取、コレステロールや飽和脂肪酸を控え、魚油の積極的摂取、節酒、禁煙のほか、
減量や運動が大切です。
減量では、BMI(肥満度)を知ることも重要となります。
BMI=体重÷身長(m)の2乗 【例】体重65キロ、身長170センチの場合、65÷(1.7×1.7)=22.4
日本の肥満度判定基準(成人)
やせ型:18.5未満 普通型:18.5以上25未満 肥満型:25以上※肥満型は1度~4度とさらに細分化されます。
BMI値が22前後が、統計的に病気にかかりにくい標準体重とされていますが、BMIは筋肉量などを考慮していない為、
筋肉質な方などは、数値が高くなる場合があります。
冒頭で説明した通り、高血圧は様々な疾患の原因となることから日頃から生活習慣に気を配る必要があります。
特に高齢者は加齢による血管の老化(動脈硬化)が起こり、弾力性を失って硬くなるたあめ、心臓が血液を送り出すたびに血圧が急激に上がりやすくなります。
血圧が高い時は、安静にすることが大切です。体を締め付けない服装で静かに過ごし、ぬるま湯で足湯をするなどして血行を促進するのもおすすめです。
ではでは!!